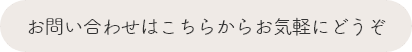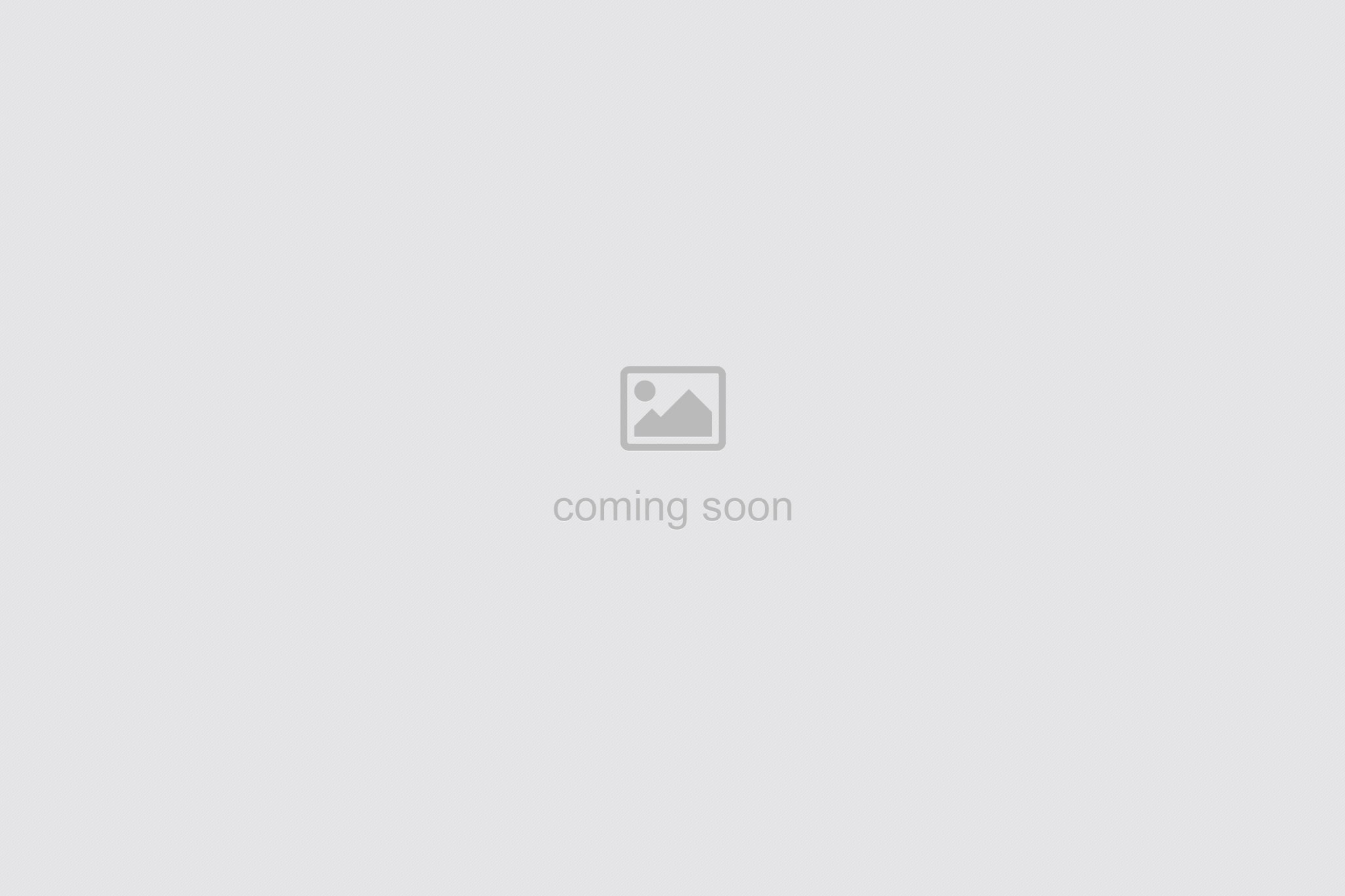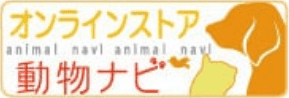今日の一言。
愛玩動物看護師の第一回国家試験、合格!
2023-03-28
ウチのTさんです。頑張りました!今までは、統一認定機構の試験を受けて合格すると認定書をもらって、動物看護師を名乗っていました。民間資格でした。今回、農林水産省と環境省が協力して国家試験を実施することにより、しっかりと専門知識を身に着けた人に、国がその仕事の重要性を認め、社会の中での位置づけを上げる、ということになりました。専門学校、短大、4年制大学が国に決められたカリキュラムを組んでいます。でもそのカリキュラムで学んでない人たちもたくさんいます。そこで、5年の移行期間をもうけ、国家試験の予備試験を受かったら国家試験の受験資格を与えることになりました。
Tさんも専門学校を卒業してから数年たっているので、受験勉強に励み、昨年の予備試験に合格し、今年2月の国家試験を受けたわけです。これからは、獣医師の指示があれば、各種注射、マイクロチップの装着、血管内留置カテーテルの挿入等いろいろやってもらえます。とっても助かります!
ドライフードの目安。「体重×10g」
2023-03-27
飼い主さんから「フードの袋に書いてある通りに計って食べさせているのに、何で太ってしまうのでしょう。」と聞かれることがあります。「おやつも与えず、ドライフードだけなのに・・・。」です。始めの頃は「もう少しお散歩時間を増やしてみます?」などと答えていました。(中には1日量の数字を1回量と勘違いしていた方もいました。「キャー」と言っていました。)でも、実際に計ってみると、結構量があります。これだけ食べれば太るよね、という量でした。そして、飼い主さんたちに、お散歩の距離と時間、家の中での行動について聞きました。皆さん毎日、朝、昼、夜と20~30分ほど歩いていました(朝、夜だけのことも)。それなりに運動していました。そこで、ある日ある時、フード会社の営業マンに聞きました。「この、フードの袋に書いてある数字、多すぎません?この通りに食べさせると、みんな太ってしまうんですけど。」すると驚愕の事実が判明しました!「この数字は毎日3回、毎回1時間走ってお散歩するコが痩せない量なんです。」そ、そんなこと、できる人いるの?「すいません、基本は欧米の飼い方なんです。」聞いてよかったー。その後いろいろ計算してみたりしましたが、一番分かりやすいのは成犬・成猫の場合は「理想体重×10g」に落ち着きました。これで痩せすぎてしまう時には運動量が多いということで、少しフードを増やします。減量成功のコ、多いです。
猫に多い甲状腺機能亢進症。
2023-03-23
中~高齢のニャンに多い病気です。食欲があってたくさん食べているし元気に走り回っているのに最近なんだか体重が減った気がする、といって来院。体重測定で、あら、かなり痩せましたねー。聴診で心拍数が1分間に240回以上(普通は140~160回くらい)。飼い主さんは「もう年だからねー。」とちょっと諦めムードです。血液検査で肝機能、腎機能に異常なし。念のため甲状腺ホルモンの量を測ってみると、基準値が0、9~3、7のところ12、0㎍/dl以上。甲状腺ホルモンが出すぎています。このホルモンは分かりやすくいうと「活性化ホルモン」で、とにかく体中の細胞を元気にします。エネルギーをたくさん使うようになるので、食べても食べても痩せてきます。目はランランとしていて声も大きく「ンガオー!ンガオー、ウギャアアー!」です(なかないコもいます)。
抗甲状腺ホルモン剤を投与します。飲み始めて2~3週間後にホルモン値を測ります。基準値に入っていれば継続、まだ高値なら薬の増量、低値なら薬の減量、となります。うまくコントロールできてくると、体重も増え、行動もおだやかになります。ひとつ注意事項があります。甲状腺ホルモンの出すぎのおかげで、腎臓への血流もよく、何の異常も無かったのが、ホルモン値が正常になって、血流がそれなりに落ち着いてくると、なんと腎不全が表に出てくることがあります。本当は腎臓の機能が落ちていたのですが、心臓がバクバクと頑張っていたので、血液検査上は腎不全が見えなくなっていたということです。その場合は腎不全の治療も始まります。7才を過ぎたら一度血液検査をしてみましょう。
前庭障害は治りますが、頭が傾いたままのことも。
2023-03-21
老犬がなり易い前庭障害(内耳炎)ですが、立てなくなったり、吐いたりするのは、水平感覚がメチャメチャになり周囲がグルグル回っているように感じて(たぶん)、酔ったような状態になるからだと思われます。眼球が横方向にキョトキョト動いてれば(水平眼振)確定です。抗生物質と消炎剤で10日もすれば吐き気などは治まってきます。歩けるようにもなるし、食欲も出てきます。あー、良かった!とホッとした矢先に、あれっ、頭が右あるいは左に傾いているのを発見。大変だー、となることがあります。これは、水平感覚をつかさどる内耳が炎症のせいで、頭が傾いたままの状態が「水平」だと認識してしまったからです。ワンによっては、15度くらいの傾きで済むコもいますし、45度も傾いたままのコもいます。それぞれ上手に食べたり歩いたりできます。ゆっくりと治るコもいればそのまま固まってしまうコもいます。みんなガンバレ!。
食物アレルギー対策は大変、です。
2023-03-18
ウチの供血犬のマグノリア(ラフコリー、避妊メス、7才)の話です。昨年の夏に身体のアチコチに皮膚炎ができて治療しましたが、治ってもまた別の所が炎症を起こすので、どうも単純な皮膚炎ではないらしい、ということで色々と検査をしました。まず、院内の血液検査で「甲状腺機能低下症」ということが分かりました。甲状腺ホルモン剤を飲ませ始めました。次に「動物アレルギー研究所」という会社が行っている「食物アレルギー検査」をしました。結果は鶏肉、豚肉、牛肉、米、卵などなど「陽性」のものがたくさんありました!びっくりです!「陰性」のものは小麦とエンドウ豆だけでした。すぐに小麦でできたドライフードを食べさせはじまました。少し落ち着いたかな、と思ったのもつかの間、2か月もするとまた皮膚炎が出てきました。むむむ、小麦にも反応するようになったのか、と思い、しからばエンドウ豆のフードじゃ、ということに。するとまた少し落ち着きました。ところが、また2か月ほど過ぎると皮膚炎が。ここでもう一度アレルギー検査を依頼しました。結果が届いてびっくり!エンドウ豆、ジャガイモ、卵白が「陽性」で、肉類や小麦、米などは「陰性」でした。小麦のフードに戻すことになりました。(甲状腺ホルモンの値は高めだったのでこちらは大丈夫)食べているものの中のたんぱく質に反応して皮膚炎になるのですが、マグノリアの場合、反応が早くて大変です。